事業内容
在宅の高齢者等及び重度身体障がい者について、火災、急病、事故等の緊急時の連絡体制を確立することにより、日常生活上の不安の解消及び人命の安全を確保するとともに、福祉の増進を図ることを目的として、市が緊急通報機器一式(本体、ペンダント型緊急ボタン、火災センサー、ガスセンサー)を貸与しています。

※画像中央が緊急通報機器本体。画像右側がペンダント型緊急ボタン。
※写真は貸与する機械の一例です。
1.緊急通報システム(緊急通報機器)とは?
24時間365日通報対応
市が委託する受信センターで年中無休で通報を受け付けます。
ペンダント型の機器もセットになっており、本体から離れた寝室等でもペンダントのボタンを押せば通報が可能です。(自宅外への持ち出しはできません)
簡単操作
ボタンを押すだけで通報できるため高齢者の方も安心です。
お伺い電話
月に1回利用者のご自宅にお電話して健康状況や生活状況を確認します。ご相談があれば、看護師や社会福祉士等の有資格者がお話を伺います。
※数日間お伺い電話で留守が続く場合、申請時に登録いただいた緊急連絡先(または緊急協力員)に連絡いたします。
通報の仕組み
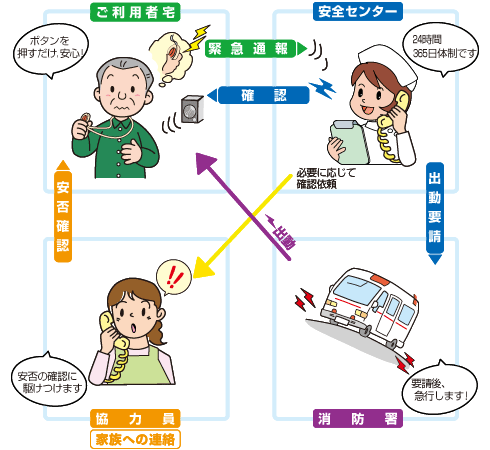
2.対象となる方
下記のⅠ~Ⅲすべてに該当する方
|
Ⅰ.千歳市に居住するおおむね65歳以上の高齢者または重度身体障がい者 Ⅱ.NTTのアナログ回線(※1)の契約があり、居宅に固定電話を設置している方 Ⅲ.以下のいずれかに該当する方(※2) ①ひとり暮らしで身体虚弱のため緊急事態に機敏に行動することが困難な方 ②ひとり暮らしで突発的に生命に危険な症状が発生する持病を有する方 ③ ①または②の身体状況に該当する方がいる高齢者のみの世帯 ④ ①または②の身体状況に該当する重度身体障がい者がいる障がい者のみの世帯 ※1 NTTアナログ回線以外の回線は非対応です。(光回線、050で始まる番号、KDDI「ホームプラス電話」、ソフトバンク「おうちのでんわ」、docomo「homeでんわ」などには設置できません) ※2 その他、同居人が勤労等のため、日中や深夜に長時間不在にする等の事情がある場合は、①に該当するものとして、設置が認められることがありますので、まずは市にご相談ください。 |
3.利用者負担費用
- 通報等の際の通話料金
※ご自宅の固定電話回線を使用して通報します。
- 利用者都合の移設に要する費用
※利用中の方が市内の引っ越し先で引き続き機器を利用する場合。
※市外へ転出される場合は撤去となります。
- 利用者の故意または過失により機器を棄損・滅失した場合の修理及び購入に要する費用
- 消防機関または緊急協力員が、火災、急病その他事故等の緊急時に利用者の救護に出動し、やむを得ない理由により当該利用者の家屋等の一部を破損し、または汚損した場合の補修等に要する費用
4.利用開始までの流れ
|
1.申し込み(電話もしくは来庁) |
| ↓ |
|
2.訪問調査・申請※1(ご自宅にて実施) |
| ↓ |
|
3.設置承認※2 |
| ↓ |
| 4.設置工事 |
| ↓ |
| 5.利用開始 |
※1 お住まいの地域の地域包括支援センターの職員が身体状況等を確認します。
(重度身体障がい者の方は、地域包括支援センターではなく障がい者支援課が確認します。)
※2 身体状況等を統一した基準で点数化し、一定の点数以上であれば「設置承認」となり、市から承認通知をお送りします。「不承認」となった場合は設置できませんのであらかじめご了承ください。
5.緊急協力員について
申請いただく際に、「緊急連絡先」のほか「緊急協力員」をご登録いただきます。
緊急協力員は、「利用者の近隣にお住まいで、利用者宅にかけつけることができる方」を基本とし、緊急通報時(相談通報時)に必要に応じて受信センターからご連絡し、利用者宅に訪問して対応をお願いすることがあります。
※救急時・緊急時は受信センターが迅速に救急車等の手配をいたします。
6.ご利用中の方へ
- 利用者本人の死亡、転出、施設入所、長期入院となった場合は、機械の返還義務が生じますので、市にご連絡ください。
- 利用者本人が死亡、転出、施設入所、長期入院となり、引き続き同居人の方が機器を利用したい場合は、名義変更に伴う訪問調査が必要になります。
※基準に満たない場合(不承認となった場合)は撤去となります。
お問い合わせ
高齢者の方、事業に関するお問い合わせ
保健福祉部 高齢者支援課 高齢福祉係
電話:0123-24-0295(直通)
重度身体障がい者の方
保健福祉部 障がい者支援課 障がい福祉係
電話:0123-24-3131(内線868)